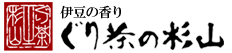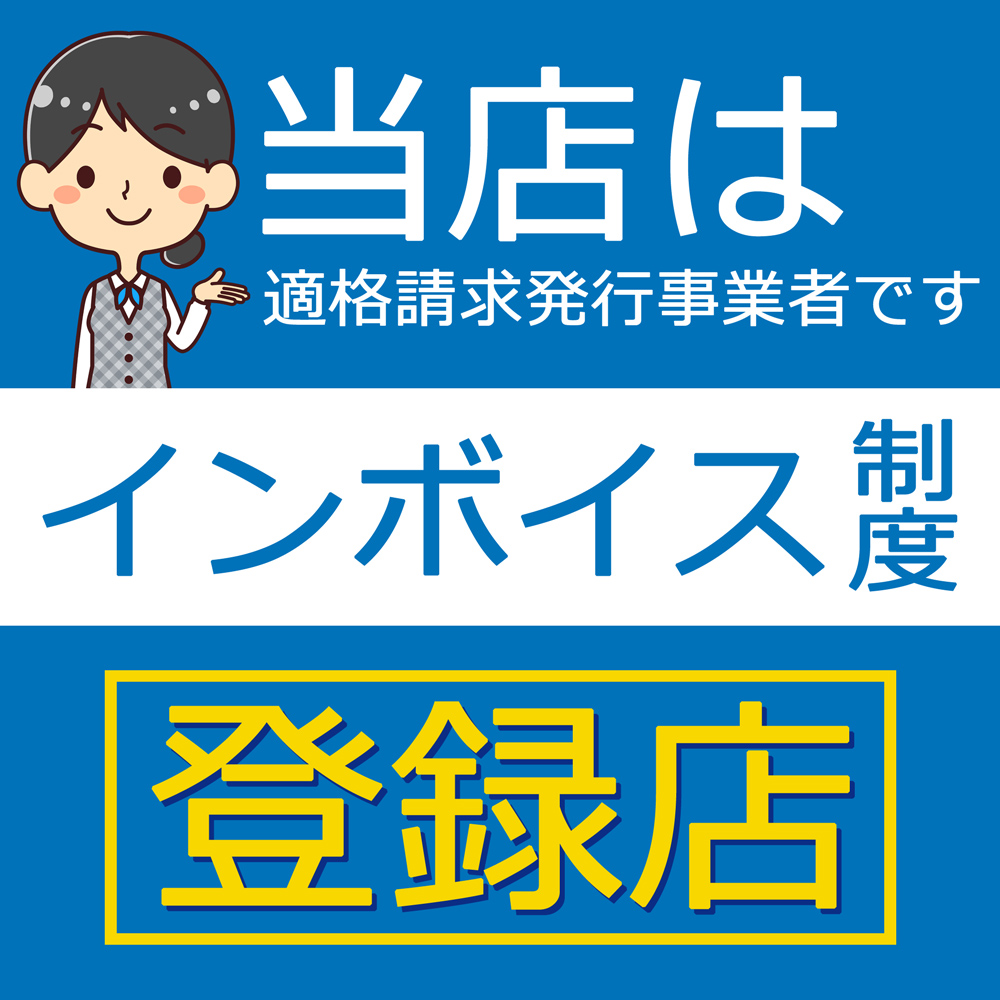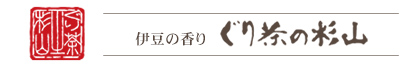被覆栽培って?
被覆栽培とは新芽の育成中に茶樹に覆いをかけ、一定期間日光を遮って栽培する方法のこと。高品質な茶葉を作る際に多く行われる栽培方法です。
茶業界用語では「被せ」とも呼ばれる手法です。
栽培期間
玉露や碾茶(抹茶の原料茶)

20日間前後の被覆栽培、もしくはそれ以上の期間行う
かぶせ茶

10日前後の被覆栽培(上記より短い期間)
被覆栽培を行う目的
被覆栽培を行う一番の目的は、お茶の「旨味」を増すことにあります。
以下で詳しく説明していきます。
濃厚な旨味
露天栽培のお茶に比べ、渋味・苦味が軽くなり甘みを感じやすくなります。
お茶の主な旨味成分である「テアニン」は、日光に当たることで渋味成分である「カテキン」に変化するという性質を持っています。
被覆栽培では日光を遮って栽培することで、テアニンがカテキンに変化するのを防ぐことができ、旨味をたっぷりと蓄えたお茶を作ることができるのです。
また、カテキンよりもさっぱりとした苦味のカフェインは、遮光することでその量が増えるため、被覆栽培のお茶は露天栽培のお茶に比べ、渋味・苦味が軽くなり甘みを感じやすくなります。
覆い香から生まれる芳潤な香り
被覆栽培を行うことによって、茶葉には「覆い香」と呼ばれる、海苔のような独特の香りが付加されます。
これは「ジメチルスルフィド」という香気成分が作られることで生まれる香りで、他の香気成分と混じり合い、お茶の爽やかな香りを作り出してくれるのです。
被覆栽培を行って作られた証拠とも言える「覆い香」は、高級茶の証とも言える香りなのです。
鮮やかで美しい水の色
被覆栽培は茶葉の色、ひいては水色も変化させます。
日光を遮ることで、茶葉はより少ない日光で光合成を行うために、茶葉中の葉緑素(クロロフィル)を増やします。
葉緑素は葉の色素なので、通常の茶葉と比べて緑色が濃くなり、鮮やかな濃緑の茶葉に育つのです。
また、少しでも日光を浴びる面積を広げるために、茶葉はより大きく、そして薄く育ちます。
通常の茶葉よりも薄く育った新芽は柔らかく、加工がしやすいため、ピンと針のように伸びた美しいお茶が作れることも、被覆栽培の目的の一つです。
被覆栽培のお茶は露天栽培のお茶に比べ、鮮やかな緑色の水の色になり、覆い香から生まれる芳潤な香り、そして濃厚な旨味を感じられる味わいが特徴です。


お茶の保存方法
お茶は、保存方法一つで品質が大きく変わってしまいます。
お茶は乾燥しているから長く持つと思っている方も多いですが、茶葉は水分含有量3パーセント程度まで乾燥させているため、空気中の湿気を吸収しやすいのです。
お茶が劣化する要因
お茶が劣化する要因はいくつかあります。
湿気と高温

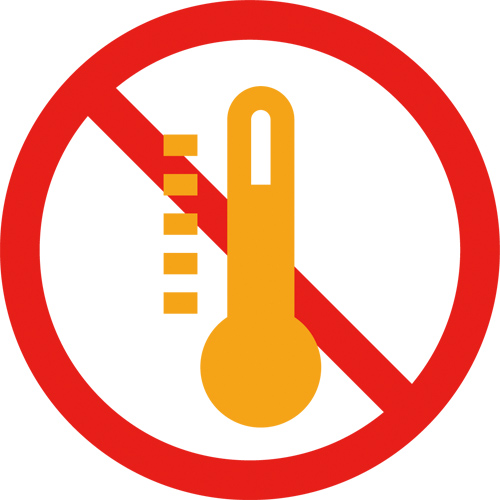
お茶が湿気を吸収すると酸化しやすくなり、茶葉の色ツヤ、入れたときのお茶の色、香り、味などが落ちてしまいます。
高温の状態にあるのも酸化を加速させる要因の一つ。
直射日光や蛍光灯の光による酸化
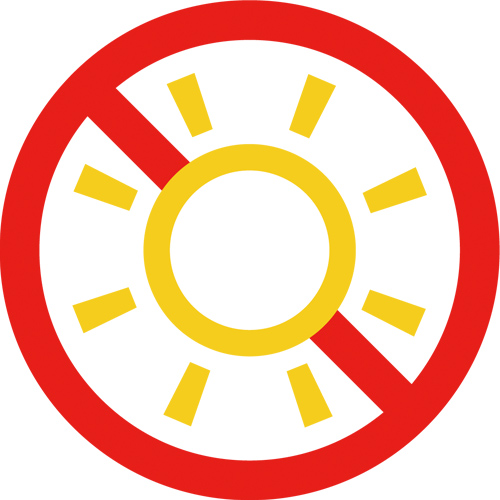
お茶は光(紫外線)、酸素、熱の影響を受けて変質してしまいます。
直射日光や蛍光灯の光に当たることで酸化が進み、カテキンやビタミンCなどの栄養素が破壊されるほか、色も悪くなってしまいます。
周囲の香りに敏感

周囲の香りを吸収しやすいので、香りの強いものと一緒に保存するとお茶本来の味や香りに影響してしまいます。
ではいったいお茶はどうやって保存するのが良いのでしょうか?
保存方法は開封前と後では異なります
基本的にお茶の保存方法は開封前と開封後で保存方法は違います。
それぞれをご説明していきます。
開封前
袋ごと冷蔵庫で、保存するのがオススメです。
実際に大量のお茶を扱うお茶工場では、大型冷蔵庫でお茶を真空状態にして保存しているんですよ。
ぐり茶の杉山では、お茶の鮮度を保てるよう袋にお茶を詰める際【窒素ガス】を封入しています。未開封の商品ならば【窒素ガス】の効果で美味しさが長持ちします。
冷蔵庫から取り出した冷たいお茶は、開封時に結露してしまうのを防ぐために、開封前に半日~1日程度かけて常温に戻してください。
折角保存したお茶が水分を含んでしまい、味や香りが落ちてしまいますので要注意です。
開封後
お茶は茶缶(茶筒)に移すか、袋の空気を抜いてしっかりとチャックをした後に冷暗所で保存してください。
さらに脱酸素剤や乾燥材などを一緒に入れておくのがおすすめ。
お茶の変質を避ける為、直射日光を避け、なるべく涼しい所に置きましょう。
光を通さない袋や容器に入れておくのもポイントとなります。
開封したお茶は、きちんと封をして空気を抜いたつもりでも、ほんのわずかな隙間から他の食品の香りが移ってしまいます。それだけお茶は匂いを吸収しやすいのです。
当店のお茶はチャック付き袋に入っておりますので、保存がし易いです。
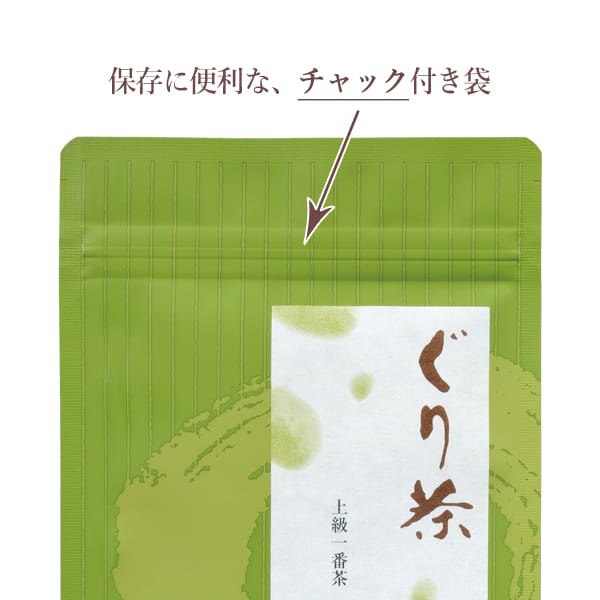
美味しく飲むために
お茶は開封後、夏季は半月以内、冬季は1か月位で開封後使い切るのがよいとされています。
パッケージに記載されている賞味期限は、あくまで開封までの期間ですので、開封したらできるだけ早く飲みきるようにしましょう。
おいしくお茶をいただくために、ぜひ今回ご紹介したお茶の保存方法をご参考ください。
HARIOハリオ社製のガラスの急須

フタなしティーポットのご紹介
耐熱ガラスで有名なHARIO株式会社の「フタなしティーポット」のご紹介です。
特徴は、お手入れが簡単ということ。
茶葉を使うとどうしても後処理に時間がかかりますがこのティーポット(急須)はさっと濯ぐだけで茶葉の処理がらくらく。
ティーポット(急須)は本体部分(耐熱ガラス製)と注ぎ口部分(PTC樹脂・シリコンゴム製)に分かれています。注ぎ口部分が従来の急須の茶漉し網の代わりの機能。

注ぎ部分のPTC樹脂とは、透明性・耐熱性・衝撃強度のある安心素材です。PC(ポリカーボネート)のような透明性を持ちながら、BPAやBPS等のビスフェノール化学物質(環境ホルモン物資)は一切使用されていない安全性の高い樹脂素材です。

注ぎ口部が簡単に取れますので茶葉の汚れが注ぐだけで簡単に落とせるのが魅力です。
本体部分は熱湯を注いでも大丈夫な耐熱ガラスとなっており、抽出している茶葉の状態が確認できます。デザインもすっきりとしガラス製ならではの透明感で素敵です。

茶葉はもちろん、ティーバッグでも便利にご利用頂けます。ひも付きティーバッグをご利用なら注ぎ部分を外して本体だけで注ぎ分けできます。
このティーポットは2種類のサイズ展開です。450mlタイプと700mlタイプとなります。
ぐり茶の杉山公式サイトで取り扱い中です。
お茶の熟成
熟成茶とは
ワインやお肉、チーズなどを美味しくする「熟成」は広く知られていますが、お茶にも熟成茶があるのをご存知でしょうか。
お茶は鮮度が大切なのでは?と不思議に思う方もいらっしゃるかもしれせんが、4月~5月の初め頃に摘みとった一番茶で仕上げた茶葉を適切な環境で寝かせることで、ワインやウィスキーなどと同じように、熟成し角が取れたまろやかな味わいへと変化していきます。春に摘んだ茶葉が夏を超えることで、青々しい香りが落ち着き芳醇な香りをまとい、角が取れたまろやかさが顔を出します。後味にもコクが生まれ「熟成」の変化が現れます。これが後熟と呼ばれるものです。
熟成茶の起源は、じつは江戸時代にまで遡ります。
駿府(静岡)に隠居した徳川家康は「お茶は貯蔵しておくと香り、味がより深まる」と言って、
春に摘んだ新茶を茶壺に詰めて密封、山間地で気温も湿度も低い井川大日峠のお茶蔵屋敷で保管して夏の暑さをしのいで後熟させました。晩秋になってお茶蔵を開き、山から駿府城まで運ばせて、お茶会を開いていたそうです。
熟成茶は薄っすら感じる甘味が舌に余韻として残る上品さが特徴ですので、当店の一口羊羹セットや、ぐり茶かすていらとも合いますので、ぜひご一緒にお試しください。
【お茶の日】って知ってる?
5月21日
みなさんはお茶の日というものが存在するのをご存じでしょうか?
1つは”国際お茶の日”で5月21日となっています。
これは国連が2019年の総会で定めたもので、お茶に関する長い歴史と文化的、経済的意義の認識を高め、お茶の持続的な生産・消費・貿易の促進を目的としたものです。
10月1日
また、日本独自のものも存在します。
1つは10月1日で、これは天正15(1587)年10月1日に豊臣秀吉が北野大茶湯を開催したことに由来しています。
大茶湯には多くの人が詰めかけ、数百人がお茶を立てたんだとか。黄金の茶室では秀吉秘蔵の茶碗や名器も展示されていました。さらに年齢や身分、国籍を問わず、誰でも参加できるものだったと伝わります。

10月31日
もう1つは10月31で、こちらは鎌倉時代に栄西が宋からお茶の種子や製法を持ち帰ったことに由来します。栄西は臨済宗の開祖で、お茶を日本に広めた人物です。

このようにお茶の日が秋にあるのは、現在では新茶といえば4月~5月ですが、秀吉が北野大茶湯を開催した頃は、新茶といえば秋だったからです。
初夏に収獲した茶葉を、壺に入れて低温で貯蔵し、秋まで寝かせる…今では「熟成新茶」「秋の新茶」などと呼ばれることもありますが、これこそが「新茶」と呼ばれていたのです。
採れたての新茶にはみずみずしい若草のような香りがありますが、寝かせることで青臭さが抜け、コク深いまろやかな茶葉に熟成されます。特に徳川家康が好んだとか。
新茶とは違う熟成茶の魅力をぜひお楽しみください!
和紅茶とは?

紅茶といえばインドやスリランカ、中国で生産されているイメージですが、実は国産でも作られているものがあります。
それらを総称したものを和紅茶と呼びます。
実は、この和紅茶は戦後すぐから生産されており、長い歴史を持った紅茶。
和紅茶と海外紅茶の違いは、日本の四季豊かな風土で育った茶葉を使っていることです。
海外の紅茶に様々な種類があるように、和紅茶も大きく3つに分類することができます。
・緑茶品種で作られた滋納(じな)|優しい味わいで和食や和菓子と相性がいい
・台湾烏龍茶やダージリンに近い清廉(せいらん)|華やかで香り豊か
・インドのアッサムやスリランカのセイロンティーを目指した望蘭(ぼうらん)|濃厚で色合い鮮やか
この内、当店の和紅茶は滋納(じな)となります。
和紅茶・国産紅茶は近年になって人気が急増し、生産量も増えているといわれますが、その始まりとなったのが鹿児島県の枕崎市です。
当店の和紅茶「日本の紅茶」はその鹿児島県の知覧産100%の紅茶です。
和紅茶は、海外の紅茶とは違う繊細で甘い香りを楽しめるので、ぜひ一度お試しください。
日本の紅茶【ひも付き】ティーバッグ16個入
8月の休業日のお知らせ
下記の通り休業日を設けさせて頂きます
■ 通信販売
夏季休業期間 2023年 8月11日(金)~15日(火)
※8/10 8:15までのご注文は、8/10出荷。それ以降は8/16出荷。
■ 直営店舗
夏季休業期間 2023年 8月26日(土)、27日(日)
※本店・伊豆高原店は終日休業

商品の発送日
2023年7月より業務効率化により商品の発送日を改定します
商品の発送は従来通りヤマト運輸です
注文確認処理は前日分(8:16~8:15)を翌営業日朝8:15に確認処理いたします。
ご注文確認後の発送スケジュールは下記通りになります。◆月曜日受注確認→火曜日出荷 ※
◆火曜日受注確認→木曜日出荷
◆水曜日受注確認→金曜日出荷
◆木曜日受注確認→金曜日出荷
◆金曜日受注確認→月曜日出荷 ※
※の発送日が改定部分です